3月11日。今年もこの日がやってきました。
東日本大震災から8年。
少しづつ日がたつにつれ、大災害へに対する備えが甘くなっていませんか?
今一度身の回りのチェックをしていきましょう。
昨年も、今すぐできる備えとして、非常食である「パン缶」に関する記事を書きました。
→3.11 震災の日に、非常食をチェック。実際に食べてみた。
今年もまた、非常食について取り上げていこうと思います。
尾西の携帯おにぎりの特徴
今回食べてみるのは、長期保存型の携帯おにぎりです。

こちらの商品は、非常食や長期保存食を多く手掛ける「尾西食品」さんの商品。
特徴としては
- お湯または水を注ぐだけで作れる
- 5年常温保存
- 手を汚さずに作って食べることが出来、衛生的
ということが挙げられます。
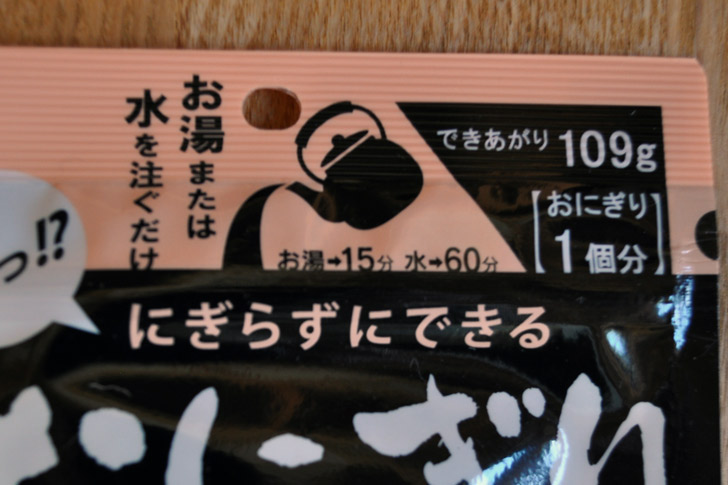
お湯でも水でも作れるというのは、良いですね。
「お湯で15分、水で60分」かかるそうです。
尾西の携帯おにぎりを実際に作って食べてみる
早速作ってみましょう。
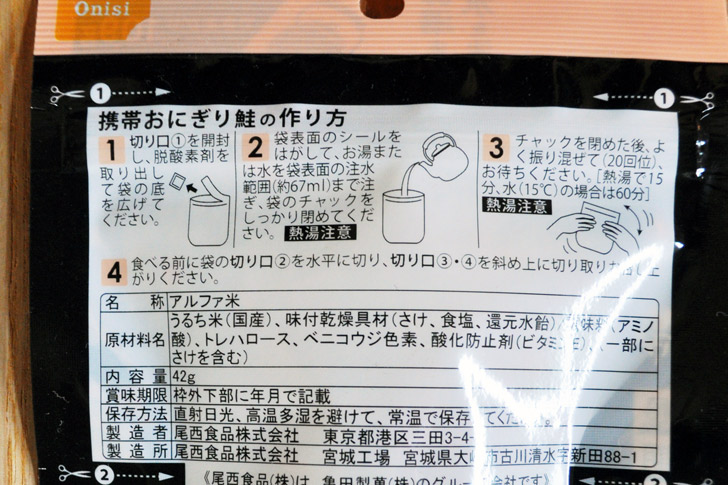
作り方は裏面を見ながら、これに沿って作って行きます。
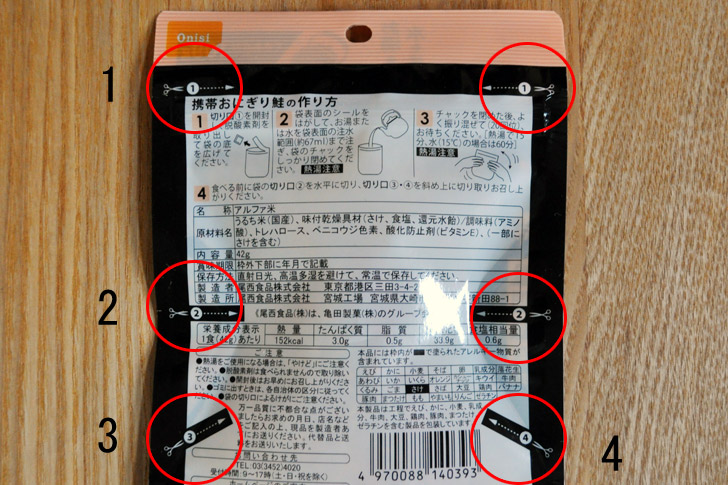
また、切り口を示すハサミマークがついています。
これもチェックしつつ、作る工程に入ります。
(1)切り口1を開封し、脱酸素剤を取り出して袋の底を広げる

切り口は手で開けられるようになっています。これ大事。

中にはアルファ米と鮭が見えますね。
一緒に入っていた脱酸素剤を取り除きましょう。
ここで底をしっかり広げておくことが必要だったのですが、私の広げ方が甘かったみたいでこの後、つぶれ気味のおにぎりが出来上がります・・。
皆さんはしっかり広げましょう。
(2)袋表面のシールをはがして、お湯または水を袋の表面の注水範囲まで注ぎ、袋のチャックをしっかり閉める。
袋の表面にはこんなシールが貼ってあります。

これをはがすと

透明になっているビニール部分に薄く赤いラインがひかれていました。
ここまでお湯をいれます。結構少ないので入れすぎ注意。(私は少し多く入りすぎました・・)
(3)チャックを占めた後、よく振り混ぜて(20回くらい)指定時間まで待つ。

こんな風に袋をよく振って混ぜます。20回くらいが目安。
私はお湯を入れたので、15分間待ちます。
(4)食べる前に袋の切り口2を水平に切り、3と4を斜め上に切り落として完成
先ほどの切り口2を開けるとこんな感じになっていました。

私がお湯を少し多く入れすぎたようで、ちょっとやわらかい感じに。
これは私のミスなので。。。

3・4の切り口を開けるとこんな感じで、そのまま食べれる形になりました。
これは手を汚さなくてよいですね。
(つぶれ気味なのは、私の袋の広げ方がいけなかったのと、水の量が多すぎたことのせいだと思われます)
水の量に注意する必要はありますが、指定された工程はとても簡単でした。
味は、違和感なく食べれました。非常食としては十分。
ただ白ご飯でなく、味が付いていることも良いですね。
これだけで食事として成り立ちます。
非常のときに「ごはん」を食べれるという安心感も持てました。
尾西の携帯おにぎりの種類
この尾西の携帯おにぎり、お味は3種類あります。
※2020年6月追記 ほかの味も増えたみたい。昆布を見かけました!

わかめ・五目おこわ・鮭です。
非常時に食べる際、味の変化がつけられるのはうれしい。
(2024/07/27 11:39:18時点 楽天市場調べ-詳細)
震災対策以外にも、登山時や海外旅行の時にも良いかもしれません。



